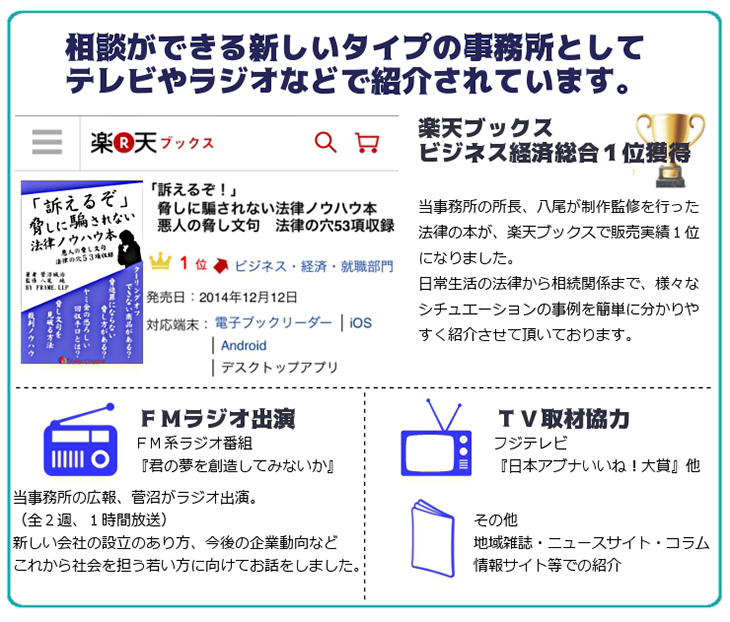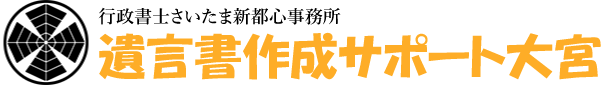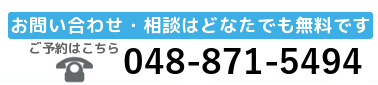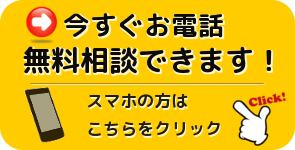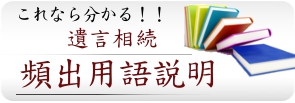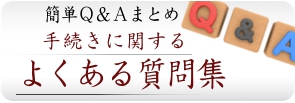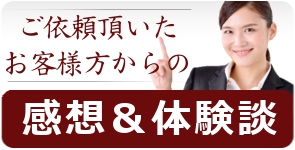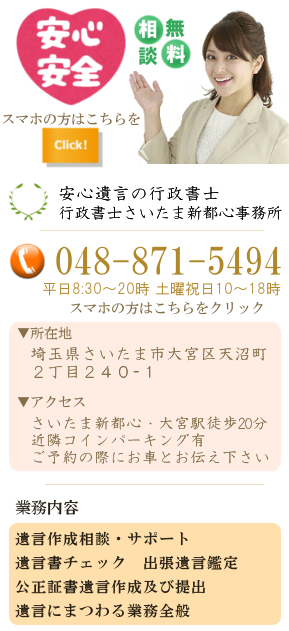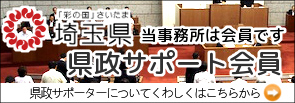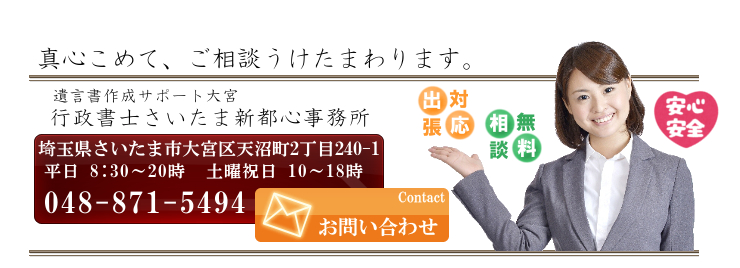争続を防止する――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】
相続で揉めてしまう原因は、相続ごとで全く違ってきます。
しかし、結局は人間関係の問題になるでしょう。
たとえば、あらかじめ相続の筋道を遺言というかたちで示しておくことで、揉めてしまうことを防ぐことができる(かもれない)のです。
遺言でできる争族対策
そもそも、遺言でできることは何か、いくつか列挙してみます。
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定
誰々は2分の1相続するとか何々を相続するとか、遺言で指定することができます。
これは、遺言でしかできません。
なお、この指定を第三者に委託することもできます。
・遺贈
相続人以外の第三者にも、遺言で遺産を贈与することができます。
ただ、遺留分には十分注意しないと、揉める元になってしまいます。
・遺産分割の禁止
おじいちゃんが亡くなって、おばあちゃんと子どもが相続人になったときなどでは、おばあちゃんが今住んでいる住居が分割されてしまうと困るようなこともあります。
そこで、5年を限度に、遺言で遺産の分割を禁止することができます。
・相続人相互間の担保責任の指定
相続人同士は、もし相続財産になにか瑕疵があった場合、その損害を担保することになりますが、遺言で別の定めをすることもできます。
・遺留分減殺方法の指定
遺留分減殺請求がなされた場合、どの財産から減殺するかは法律で定められていますが、遺贈については遺言で別の定めをすることもできます。
・相続人の廃除
虐待などをしてきた人が相続人になるのは許せない!というときは、廃除をすることができます。
これは遺言でもできますし、生前にあらかじめ廃除を申し立てることもできます。
・遺言執行者の指定
遺言の内容を実現してくれる人を遺言で指定することができます。
身内の人に頼んだほうが良い場合と、全く関係ない第三者に頼んだほうが良い場合があり、誰を指定するべきかというのは難しい問題です。結局は、揉め事を防ぎつつ、相続を円満に済ませることが第一ですから、それを基底において考えればいい話です。
・子の認知
生前に認知することもできますが、遺言で認知することできます。
・祭祀承継者の指定
お墓や仏具などを誰が承継するかを指定することもできます。